![]()
≪タヒノトシーケンスの考察 第4回≫
キャラクターが人間になるとき
こんにちは。丘本さちをと申します。
第4回目の考察は、記号が散らばるタヒノトシーケンスの中で、「記号化していないもの」について勝手にカイセツしてまいります。ですが、正面突破は芸が無いので、アクロバティックな回り道をしながら考察を進めていきましょう。最終回なのでちょっと長いです。ご了承ください。
劇場版アニメ『君の名は。』が大ヒットしています。
このカイセツを読んでいる方の中にも、ご覧になった方は多いと思いますが、同作で特筆されることのひとつに、写実的で精細な背景美術があります。
一般的に、アニメーションとはイラストが動くものです。イラストというのは実際の物質や現象を、単純な線や色に抽象化して表現した図像のことです。この抽象化の度合いを深めていくと、図像はイラストを通り越して「記号」になります。例えば、人の顔がニコちゃんマークになったりします(^_^)。
(本当は「象徴」というべきなのですが、このカイセツでは分かりやすさ重視で「記号」という言葉を使います)
さて、『君の名は。』の背景は、アニメとは思えないほど具象的に描かれています。でも、こう言ったら怒られるかもしれませんが、人物は割とありがちなイラストタッチです。これは前回のカイセツにならって言うと、背景と人物の抽象化・記号化のレベルをズラしている、と言えます。タヒノトが舞台上の記号化レベルを揃えているのと逆のパターンですね。
この記号化のレベルを(意図的に)ズラすという手法、実はスタジオジブリの『おもひでぽろぽろ』という作品でも行っています。『おもひでぽろぽろ』は、主人公が生きる当時の現代と、主人公の子供時代の思い出が交互に描かれていきますが、現代パートは人物も含めて写実的、思い出パートは色使いも淡く、人物もイラストに近くなっています。
しかし、現実と回想、はっきりと世界が別れるところでレベルをズラす『おもひでぽろぽろ』と違って、『君の名は。』は同一の舞台上で抽象化のレベルをズラしています。何故そんなことをするのでしょう?
それは同作が、舞台設定(世界観)をリアルな現代日本としつつ、人物を抽象的な存在として描いているからです。ですがここで疑問が発生します。『君の名は。』の主人公は一般的な現代の高校生。一体なにが抽象化されているのでしょうか?
抽象化というのは、「複雑なものの枝葉をそぎ落とし、特徴を抽出すること」です。だから複雑な形状をしている人間の顔が、(^_^)となります。裏を返せば抽象化とは、単純化とも言い換えられます。
『アンパンマン』のような児童向けアニメを考えてみましょう。
アンパンマンの見た目は、まさに記号といっていいほど抽象化(単純化)されています。そのほうが、いついかなる時でも幼児がアンパンマンを認識できるからです。そして同じように、アンパンマンの「内面」も抽象化(単純化)されています。アンパンマンの行動はいつも変わりません。困った人がいれば必ず助けますし、お腹が空いた子供がいれば急いで顔を食べさせます。楽しい時には必ず笑い、悲しいときには素直に泣きます。「今日は人助けなんかしたくない」などとは絶対に言いませんし、楽しい気持ちを押し殺したり、悲しいときに笑ったりする複雑さも持ち合わせていないのです。
『君の名は。』に戻って言うと、同作の登場人物は外見だけではなく「内面」も抽象化され、複雑さを切り捨てた存在になっているのです。だから現実離れした出来事が起こっても、繊細な感情の動きがなく、素直に受け入れてしまえるし、入れ替わる度に同じような反応をします。もし現実で思春期の男女の体が入れ替わったとしたら……驚く程度じゃすみませんよね。
この外見や内面が抽象化され、記号としてスタティックな状態(状況を通じて一貫して内容が維持された状態)にあるものを「キャラクター」と言います。
ミッキーマウスのデザインは変わりませんし、俺様キャラのジャイアンはいつものび太をどやしつけるわけです。
もちろん、逆に外見が抽象化されていても、内面が複雑というケースもあります。青年向けの漫画やアニメはむしろそちらのほうが多いでしょうし、日本のサブカルチャー/オタクカルチャー作品がハイクオリティである所以もそういったところにあると思います。
ずいぶんと回り道をしているように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。このカイセツのテーマは、記号が散らばるタヒノトシーケンスの中で、「記号化していないもの」について。
タヒノトシーケンスは『君の名は。』の逆だと考えましょう。つまり、記号的な舞台表現の中で、人物の「内面」がリアルで具象的だということです。
しかし、それも一筋縄ではいきませんので、段階を追ってカイセツしていきす。
まず、タヒノトシーケンスには登場人物の「キャラクターシート」というものがあります。これはWEBにも公開されているのでぜひご覧いただきたいのですが、一言で説明すると、登場人物の履歴書になります。氏名、性別、年齢に始まり、学校歴・職歴や趣味嗜好などの属性、他の登場人物との親密度までがステイタスとして記述されています。つまり人物を、特徴を抽出した「キャラクター」、としてタヒノト世界に登録しているのです。
タヒノトシーケンスのドラマツルギーは、「田丁町」の持つ特殊な能力を縦糸とし、登場人物同士の「コミュニケーションの失敗」を横糸として編まれていきます。縦糸である田丁町の能力に対しては、登場人物は「キャラクター」として応対します。不可思議なことが起これば、昔からの町民は「そういうものだから」と受け入れ、諦めたり、面白がったり、利用しようとしたりします。逆に田丁町に馴染んでいないビジターの場合は、「どうしてだ」と訝り、怒り、惑わされ、途方に暮れます。縦糸の軸で紡がれるのは、ロジカルでウェルメイドな構成のコメディです。
しかし、面白いことに横糸の「コミュニケーションの失敗」に対して、登場人物の心情や感情は削ぎ落とされていません。複雑でリアルなままなのです。
「キャラクター」というのは、記号としてスタティックな状態(状況を通じて一貫して内容が維持された状態)であると書きました。それは言い換えると、ブレない状態、迷わない状態でもあります。つまり「キャラクター」は精神的に変化をしません。横糸の軸で紡がれるのは「コミュニケーションの失敗」による人間的な苦悩や変化、そして成長によるエモーションの顕現。突然の不意打ちのようなドラマです。そのようなドラマを描くためには、記号化されない、複雑な、「人間」が舞台にいる必要がある。舞台公演タヒノトシーケンスの一番の凄みは、この記号化されない人間の心情を「コミュニケーションの失敗」という痛切な刃で抉り取っていく部分にある。僕はそう考えています。
不可思議な地方都市「田丁町」。
そこで巻き起こるシュールでコミカルな超常現象。
翻弄される、どこか歪んだ「キャラクター」達。
彼ら彼女らが、心の揺らぐ「人間」として立ち現れ、震えるとき、観客である私たちの胸の内も、大きく揺さぶられずにはいられないのです。
了
(丘本さちを/週末小説家/ケシュ ハモニウム副主宰)
![]()
≪タヒノトシーケンスの考察 第3回≫
舞台表現の記号化
こんにちは。丘本さちをと申します。
タヒノトシーケンスの考察、第3回はタヒノトの舞台表現について勝手にカイセツをしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお付き合いください。
さて、タヒノトシーケンスの舞台表現について何を面白がればいいのか。
このカイセツを読んでいる方の中で、『タヒノトシーケンス Vol.1 透明な動物と夜通し歩き回る』をご覧になった方がいれば、まず「プロジェクションマッピング」のことが頭をよぎるのではないでしょうか?
ほぼ素舞台のステージに、時計やテロップ、雨や風などの特殊効果のアニメーションが投影されていく。それがタヒノトシーケンスの舞台美術になります。
この手法は、作者の仲井陽いわく「演劇にかけるコストをミニマムにする」という制作コンセプトから生まれたらしいのですが、僕はそれをオモテの理由だと思っています。つまり制作面からの発想ではない、作家としての、創作面からのウラの理由があるということです(本人が意識しているかどうかか分かりませんが)。
もう一度、第1回の考察を思い返してみましょう。
タヒノトはその世界観を愉しむ・愉しませるために、「町」そのものを「舞台」にしている、すなわち「世界観」をまるごと「舞台」に上げている、と書きました。
どんな創作物も、作家の脳内にあるストーリーやイメージ、その他のさまざまなアイデアは、すべからく「表現」に落とし込み、アウトプットされなければなりません。小説なら文章を書く、映画なら撮影して編集する、そして演劇なら舞台装置を建て、役者に演技をつける。そういった頭の中のアイデアを目に見えるように具象化することが必要になります。
ですが、果たして「田丁町」という「町」ひいては「世界観」そのものを演劇の舞台上で具象化することなどできるでしょうか? 現実的に考えて不可能です。書き割りで処理したり、シンボリックな舞台装置を建てるという手もありますが、雨や風などの自然現象にまで至るともう、どうにもなりません。あるいは、ある場所からある場所へ移動していく、地方都市ならではの間延びした空間(もちろんこの空間も田丁町の一部です)、これを具体化するのも難しい。
つまりタヒノトの舞台美術が素舞台にプロジェクションマッピングなのは、舞台に上げるもの=「世界観」のすべてを具象化することが、そもそもできないからなのです。
「町」を物理的な舞台装置によって具象化する代わりに、タヒノトは、テロップやイラストアニメーションという「記号」をステージに投影することで、抽象的に世界を(まるごと)立ち上がらせているのです。
この「記号」が、タヒノトの舞台表現を語る上でとても重要なキーワードなのですが、いったん話を脇に進めましょう。
僕が今回の公演の稽古にお邪魔した時のことです。
ある役者がフランクフルトを食べる演技をしていました。タヒノトの舞台には基本的には持ち道具も消え物(演技の際に飲み食いする食事)も出てこないので、必然的に役者はパントマイムで「フランクフルトを食べること」を表現することになります。
で、フランクフルトは食べ終わると手元に串が残りますよね。役者の生理としては、この食べ終わって手元に残った串をどうしようかと悩むわけです。ゴミ箱に捨てにいこうか、このまま足下に放ってしまおうか。迷っている役者に、作演の仲井陽はこう言います、「そのまま消しちゃっていいよ」と。「マイムじゃなくて、食べたっていう『記号』があればそれでいい」。
そう言われた役者は目を白黒させていました。そりゃあそうです。役者にしてみれば演技を途中で放棄しろと言われたようなもの。
が、僕はピンときました。
パントマイムは実際に道具を持って芝居をするよりも、抽象的な演技です。しかし、仲井が役者に求めていたのは、パントマイムよりも、もう一段階抽象的、記号的な演技であり、どちらかというと「ジェスチャー」に近いものです。
先に述べたように、演劇は照明や音響を含んだ大きな意味での舞台装置と、役者の演技が表現のアウトプットになります。タヒノトの舞台装置は素舞台に「記号」を投影することで、世界を作っていました。ならば、もう一方である役者にも「記号」的な表現をあてはめることが必要になってきます。だからパントマイムではなく、より記号的な「ジェスチャー」をさせている。
つまり、舞台上の抽象化・記号化のレベルをきちんと揃えているのです(もし舞台装置がプロジェクションマッピングではなく、書き割りのようなもっと具象的なものだったとしたら、役者は普通にパントマイムをしていると思います)。
この記号性は通行人や店員などの「モブキャラ」や、衣装にも如実に反映されています。どのように反映されているのかは公演を見てのお楽しみ、ということにさせていただきましょう。
タヒノトシーケンスの舞台上にはあらゆる記号が散らばっていますが、最後となる第4回では、逆に記号化されていないものに焦点をあててカイセツしていきたいと思います。
つづく
(丘本さちを/週末小説家/ケシュ ハモニウム副主宰)
![]()
≪タヒノトシーケンスの考察 第2回≫
TRPGシステム
こんにちは。丘本さちをと申します。
前回に引き続き、『タヒノトシーケンス』の“勝手なカイセツ”を進めて参りましょう。今回は少し難解な内容になってしまっているのですが、興味のある方はどうぞお付き合いください。
さて、第1回ではタヒノトシーケンスの舞台となっている田丁町という町が、サブカルチャー/オタクカルチャーに根ざした「世界観消費」の系譜を受け継いでいること。そして他のメジャーな世界観消費系の作品群と異なり、タヒノトは超常的な能力を持っているのが、「人では無く、町そのもの」ということに言及しました。
第1回を書いた後に、他にも町そのものが特殊な能力を持つ作品はないかと記憶をあれこれまさぐってみたのですが、やはりうまく思いつかず。
劇場版アニメ『うる星やつら ビューティフルドリーマー』、『千と千尋の神隠し』、ゲーム『SIRENシリーズ』が近いのかなぁ、と思ったりもしたんですが、これらは「異界」に閉じ込められ、そこから脱出する話なのでちょっと違うように思われます(いわゆる異界訪問譚ってやつですね)。
でも、実を言うとただひとつ例外的な作品があります。
それは藤原カムイ氏の漫画『福神町綺譚』です。
同作の舞台である「福神町」も特殊な能力を持つ町であり、「町」が住民の生活に多分に干渉していくことで、群像劇のストーリーを成り立たせています。
が、タヒノト作者の仲井陽と、タヒノトに推薦文を寄せていただいた藤原カムイ氏とのつながりが示すとおり、田丁町の発想の源泉が福神町なので、ここで両作の世界構造の類似性を解いても有意ではありません。
ひとつ面白いのは、福神町綺譚では「町の成り立ちを巡る謎」が作品全体を貫く大きなストーリー軸になっているのに対し、タヒノトシーケンスには「その大きな物語」すら無いことで、ここがまさに“今”っぽいデータベース的な作り方になります。が、その説明を始めると長くなるので、ここでは割愛します。私たちが着目するべきは、両作の「世界構造の類似性や相違点」ではなく、その世界の「作り方の類似性と相違点」にあるからです。
タヒノトシーケンスのエピソードは、出演者参加型のTRPG(テーブルトーク・ロールプレイングゲーム)形式によって作られています。
Wikipediaを参照しながらTRPGの説明をすると、
「TRPGとはゲーム機などのコンピュータを使わずに、紙や鉛筆、サイコロなどの道具を用いて、人間同士の会話とルールブックに記載されたルールに従って遊ぶ対話型のロールプレイングゲームを指す言葉である。
一人は通常、自分のプレイヤー・キャラクターを作らず使わず、一般にゲームマスターと呼ばれる役を受け持つ。
ゲームマスターは他の参加者と対話しながらゲームの舞台となる世界とそこに登場するいろいろな事件や人物を説明し、決められたルールに従って、プレイヤーが考えたキャラクターの行動が実現したか否かを裁定することでゲームを進行させる。単純化して言えば、コンピュータで遊ぶRPGでの、コンピュータ役をゲームマスターという人間が担当するのがTRPGだといえる。」
タヒノトシーケンスは、作者=ゲームマスターである仲井陽が用意した「田丁町」という架空の地方都市に、出演者が一キャラクターとして参加し、ゲームマスター仲井陽の干渉や誘導を受けながらエチュード(即興芝居)をすることで、エピソードが紡がれていきます。
このエチュードを行う会は「稽古会」と呼ばれ、基本的には誰でも参加可能です。そして、誰が参加しても滞りなくストーリーが展開できるように、ルールやシステムが組まれています。(注:公演では、稽古会で出来上がったエピソードや人物同士の関係性を下敷きにして台本が作られます)
また福神町綺譚も、インタラクティブ・コミック(双方向性漫画)として連載され、毎回のエピソードは読者投稿やネット上の「福神町会議室」を中心に作り上げられるという方法が取られていました。
両作はこのようにとても似通った作り方をしています。
が、福神町が参加者から提供されるのが「アイデア」なのに対し、タヒノトは参加者が自分の意志でキャラクターとして「自由演技」するところまで踏み込んでいます。つまり作者ではなく、参加者が自分たちでストーリーや人物関係のアウトプットを(未完成かつ暫定的であるとはいえ)出していくということです。
- 福神町綺譚は、作者個人にインプットし、作者個人がアウトプットを返す。
- タヒノトシーケンスは、参加者多数にインプットし、参加者多数が返したアウトプット(即興芝居)を、作者個人にインプットして、作者個人が最終アウトプット(台本)を返す。
通常の創作物(福神町綺譚を含む)であれば、登場人物は大なり小なり作者個人のアウトプットの一部なので、人格や行動は作者の描くままですが、タヒノトは登場人物(参加者)が、作者から独立した状態で始まるわけです。加えて、作者=ゲームマスターは舞台には立てない外野の存在。
この状態で作者=ゲームマスターがストーリーを前に進めたり、制御したりするためには、タヒノトにおける「ゲームのルール」の力を利用するしかありません。この「ゲームのルール」は色々あるのですが、そのひとつとして「田丁町の不思議なモノ・ヒト・コト」が存在しています。
各々のエピソードの核になるのは、必ず「田丁町の不思議なモノ・ヒト・コト」であり、誰もその設定を無視したり書き換えたりすることは出来ません。これは絶対のルールなのです。
そして、常識外れな超常現象が起こる町であるにも関わらず、超能力を持つキャラクターが出てこないのは、ストーリーを制御する上で登場人物が「ゲームのルール」を破れないようにするため。言い換えると、ゲームマスターと参加者のパワーバランスを常に「ゲームマスター>参加者」に固定するため、だというのが僕の仮説です。
タヒノトシーケンスはこのようにTRPGの手法に立脚するが故に、構造的な縛りが出てくる部分が他にもあるんですが、それはまた別の機会にカイセツできればと思います。
うーん、ずいぶん抽象的でお堅い話になってしまいました。
次回は話題をもっと具体的でポップな方向に振って、タヒノトの舞台表現の手法について勝手なカイセツをしていきたいと思います。
つづく
(丘本さちを/週末小説家/ケシュ ハモニウム副主宰)
![]()
≪タヒノトシーケンスの考察 第1回≫
「町」を「舞台」にすること
こんにちは。丘本さちをと申します。
ふだんは短編小説を書いている一個人なのですが、ここだけの話、僕には悪いクセというか、いかがわしい趣味があるんです。それは、創作物を「どうやって見たら面白がれるか」を自分勝手にカイセツすることです。
小説、映画、漫画、アニメ、アートと表現の形態を問わず、「これはこう見たら面白い!」「これは言い換えればこういうことだ!」。そんな発見をすることに、どことなくシニカルな悦びを感じてしまうんです。
レントゲン写真を撮るように、創作物の構造・骨子を捉えて、肉付けを変えていく。あるいは記念写真の世界に入り込んだみたいに、カメラを見つめて並び立つ人々の傍らに忍び寄り、その横顔を盗み見ていく。
ともすれば人の機嫌を損なうような悪いクセですが、まあ好きなんだから、しょうがないですね。すみません。
さて、個人的な前置きはこれくらいにして、早速『タヒノトシーケンス』の考察に入っていきたいと思います。
いよいよ第二回目の公演を迎えるこの作品を、一体どう見たら面白がれるのか。自分勝手にカイセツしていきます。(田丁町観光課からは、「ネタバレなしで」って言われてるんだけど、具体的な内容に触れずに考察を書くのってかなりの知識と技量を要するので、正直、タイピングする指が吊りそうなくらい辛いです)
捉え方の切り口は色々あります。が、ざっくり4回くらいに分けてつらつらと書きとどめます。
第1回目は「町」について。
田丁町という架空の地方都市で巻き起こる、奇妙なエピソードの積み重なりである『タヒノトシーケンス』。その主人公は誰か?
それは田丁町という「町」そのものだと言えます。
各エピソードによって主人公格の登場人物は存在するものの、それはその場限りの狂言回しにしか過ぎません。幕が移れば、また別の人間が物語のナビゲーターとして登場することになります。
この「不思議な町で暮らす人々の群像劇」という仕立てを持つ作品、他にもいくつか思い当たる方もいるのではないでしょうか。例えば漫画では『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』 や『鉄コン筋クリート』、ちょっと古いけど映画『スワロウテイル』、最近ではライトノベルの『とある魔術の禁書目録シリーズ』、意外と気づきにくいところではアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』もその範疇に入ります(エヴァは第三新東京市で暮らす人々の物語です)。
こういった空想の世界観自体を愉しみ、時にはその世界設定に沿ってスピンオフや二次創作を生み出すことを、21世紀のクールジャパンに生きている私たちは自然なリテラシーとして身につけています。つまり、田丁町は1980年代から2000年代にかけて、サブカルチャー/オタクカルチャーが醸成してきた「世界観消費」の系譜をそのまま受け継いでいるといっていいでしょう。そして、タヒノトシーケンスは田丁町という「世界観」をそのまま文字通り「舞台」にしてしまいました。これはかなりの直球です。架空の「町」を「舞台」にするということは、「世界観そのもの」をまるっと「舞台」にするという力技以外の何者でもないのです。
で、面白いのが、一見すると先に挙げたジョジョ以下のポピュラーな作品群と同じ構造を持つように見えるタヒノトですが、よくよく考えてみると実はまるっきり逆だということです。
何が逆なのか。
先の作品群は、「特殊能力を持つ人が変わった町に住んでいる」あるいは「特殊能力を持つ人が町を変わった場所にしている」のですが、タヒノトは「特殊能力を持つ町に変わった人が住んでいる」のです。
超常的な能力を持っているのは、人では無く、町そのものなのです。その顕著な例が自然現象です。田丁町には昼が夜のように暗くなる「黒昼(こくちゅう)」や、槍が降っているかのような勢いの「槍雨(やりさめ)」、立っていられないほどの強風「栂倒し(つがだおし)」といった田丁町にしか起こらない自然現象の設定があり、登場人物を翻弄します。まるで町自体がスタンド使いのようです。
「町」と「町の付属物(建築物や自然や動物)」が起こす災禍や福音が、性格的にどこか歪んだ住人たちに降りかかっていく、これがタヒノトが持つ基本的な構造です。
ではどうしてこのような構造を持つに至ったのか。
それはタヒノトシーケンスの成り立ちが、出演者参加型のTRPG(テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム)形式であることと無関係ではありません。
漫画や映画になくて、TRPGにあるもの。それは「ゲームマスター」の存在です。田丁町の能力はゲームマスターの能力とほぼ同義なのです。
次回は、そのTRPGシステムの切り口から、タヒノトシーケンスを考察していきます。
つづく
(丘本さちを/週末小説家/ケシュ ハモニウム副主宰)
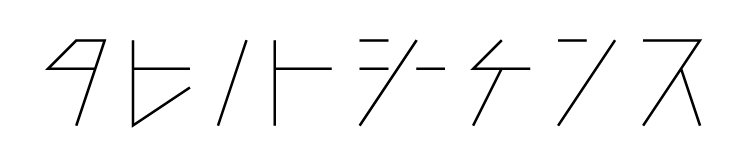
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)