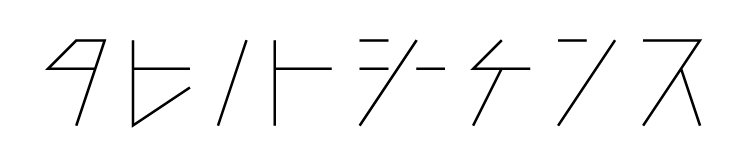≪前編≫ 高梨佐緒里の
「タヒノトシーケンスのちょっと変わった見方――まちの情報とネットワークに着目して」
K県田丁町。ちょっと奇妙な地方都市。
タヒノトシーケンスを見る場合、プロジェクションマッピングを使った独特の演出や、物語の情感などを楽しむことももちろんありえる。
しかし、Webを見てみると「まちの情報」が膨大に公開されている。これは何なのだろうか。多くの人は面倒で読み飛ばしてしまう情報であるが、これをあえて公開する意味とは何だろうか。
同時に、キャラクターシートという自己紹介書(住民票)には、「知り合いとの距離」が書かれている。多くの場合、私たちは演劇を見ていくうちに登場人物同士の距離を知ることになるが、このようなかなり詳細な「相関図」の情報を先に公開する理由は何だろうか。
ここでは田丁町住民でもある筆者(今回はでません)が、この2つの観点から、「タヒノトシーケンス」のもうひとつの見方について提示してみたい。
------------------------------------------------------------------------------------------
ある人がどこに生まれ育つのか、ということはほとんどの場合選べない。だからこそ、人々の生活において、「地域」、「生まれ育った/現在住んでいるまち」というのは重要な要素である。しかし、演劇を見る際、あるいは作る際、わざわざその住んでいるまちまで気にすることはあまりない。観客は、主人公の移動手段や、買い物の様子、あるいは会話の断片からそれを推測することしかできない。
一方、このタヒノトシーケンスは、「まちの情報」が詳細に開示されている。つまり、物語を見る前に、彼らが住んでいるまちについて観客は知ることができるのだ。
想像の共同体、とは、ベネディクト・アンダーソン【※1】が提唱した概念であるが、それによれば私たちはたとえ会ったことのない人々でも「新聞」・「雑誌」などのメディアをもとに、あるいは「国旗」・「共通の言語」などのシンボルをもとに、「1つの共同体(国家)」の一員であるということを自覚しているという。つまり、国家とは実体のない存在(=虚構)なのである。
この考え方を逆手に取ったような作り方が、田丁町、あるいはタヒノトシーケンスなのである。まちに関する大量の情報を、程度の差はあれ「共有」していれば、誰でもこの架空のまちの住民になれる。まちが虚構であるから、情報を共有していればだれでも町民になれるのだ。そしてこの街の情報自体、脚本家のみならず、参加者たちによって(勝手に)作られていったものだ。例えば、野外劇、街を舞台にした演劇はこれまでにもあった。しかしタヒノトシーケンスは「架空のまちの情報」を開示するということで、誰でも住民になりうる要素を持ち、そのことを通じて作り手と観客の距離を曖昧にしようといえよう。
※1:ベネディクト・アンダーソン(Benedict Anderson):1936年生、アメリカ人の政治学者。主著はImagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,([1983]2006、白石隆・白石さや訳、2007『定本 想像の共同体――ナショナリズムの起源と流行』書籍工房早山)。
田丁町舞網在住(危篤薬局勤務) 高梨佐緒里
(髙橋かおり/文化社会学/http://researchmap.jp/k.artkhs/)
≪⇒後編に続く≫
.jpg)
田丁町のみつけかた
・・・連作短編演劇プロジェクト「タヒノトシーケンス」をより楽しむために、いろんなひとがあらゆる角度から、ちょっと語ってみるコラム。

≪後編≫ 高梨佐緒里の
「タヒノトシーケンスのちょっと変わった見方――まちの情報とネットワークに着目して」
ところで、社会学や地域研究者、文化人類学者など、地域をフィールドとして研究する者は、地域を調査する際、人にアプローチし、あるいは地域に関する資料を読み解きながら、その人的ネットワーク構造(誰と誰が親しいのか、誰が最も多くの人とつながっているのか)ということを明らかにする。加えて、地域に関する歴史や現状に関する情報も調べる。これらの過程を通じて地域の歴史や現状を知ろうとするのだ。
しかし、このタヒノトシーケンスの場合、地域の歴史や常識を知った人々がネットワーク構造を「作り出し」、そこから物語を「生み出す」、という、研究の手法からすると奇妙なことが起こっている。つまり、研究者は「ある実態」(=現実)に対して存在している「骨組」を取り出そうとするのだが、タヒノトシーケンスの場合は「骨組」を先に作ることによって、架空のまちの「ある実態」(=物語・虚構)を作り出す。そして両者ともその全体には「まちの記憶」・「まちの情報」があるのだ。
そして今回の登場人物のネットワークを描いてみると、そこからさらに物語が読み取れる。例えば、多くの人とつながりを持っている米原と矢崎は、それぞれに「役場職員」と「医者」という、多くの人とのつながりを持ちうる職業である。特に米原の場合、だからこそ彼の元に様々な情報が集まる。この「ハブ」となる人の活躍は、物語の展開に欠くことができない。他方、田丁町に来たばかりの野田はまちとのつながりが薄い。キーとなる人物にたどり着くまでに何人も経由しなければならない。そのため、なかなか問題が解決しない。これは結婚を機に田丁町に来た仙田寅雄も同様だ。トラブルが起こったときに、数少ない薄い関係(弱い紐帯)の人に頼らざるを得ないのである。その人の性質に問題解決の成否が大きく左右されるのである。
このつながり(紐帯)の過多は物語の展開に大きく関連している。そのような点から物語を見直してみると、登場人物の選択に合理性が生まれてくるのではないだろうか。なぜなら、彼らの物語にはこのような関係が先にあるため、「その関係でその会話内容は親しすぎるのでは(あるいは疎遠すぎるのでは)」ということが起こりえない。そしてこれらの関係のネットワークが、自身の行動の裏付けになっているのである。
そのほかネットワーク論においては例えば、「6次の隔たり」(どんな見知らぬ2人でも、間に5人を介せば到達することもできる/スタンレー・ミルグラム【※2】)、や「弱い紐帯の強さ」(転職活動においては、血縁など強い紐帯ではなく、遠いあるいは弱い紐帯の方が効くのであり、これを多く持っているほうが最終的に成功しやすい/マーク・グラノヴェッター【※3】)などの理論があるが、これらのことを頭の片隅に入れながら物語を見てみるのも、また興味深いだろう。
まちの情報と関係性のネットワーク。この2つは、研究者がまちを探求する際に明らかにしようとする「データ」である。タヒノトシーケンスでは、このような「データ」を先に作って共有し、そこから物語を生み出そうとする。研究者はこのデータからまちの状況(=現在)を描き出そうとするのだが、タヒノトシーケンスの参加者はそこからさらに新たな物語の展開(=未来)を描くのである。同じ材料でも、アプローチの仕方が違う。そのような観点で物語を見てみると、また新たな発見があるのではないだろうか。そして、自分がすむまちへの見方も、変わるきっかけを持ちうるのではないだろうか。
田丁町はどことなく不可思議で奇妙な雰囲気がただよい、一見狂っているように見える。しかし、人々が適切に、安心して狂うためには、このような緻密なまちの構造(共有するまちの情報や関係性のネットワークの把握)という強固な基盤が不可欠なのである。
※2:スタンレー・ミルグラム(Stanley Milgram):1933年生、アメリカ人の社会心理学者。本稿で参考にしたのは, “The Small-World Problem”, (1967, Psychology Today,Ⅰ:61-67、野沢慎司・大岡栄美訳、「小さな世界問題」、野沢慎司編・監訳、2006、『リーディングスネットワーク論――家族・コミュニティ・社会関係資本』勁草書房:97-117)。そのほか、倫理的に問題となったアイヒマン実験(閉鎖的な状況で被験者が権威者に服従するかどうかを暗に測定した実験)などでも有名。
※マーク・S・グラノヴェッター(Mark Granovetter):1943年生、アメリカ人の社会学者。若くして“The Strength of Week Ties.”(1973,American Journal of Sociology, 78, 1360-1380、大岡栄美訳、「弱い紐帯の強さ」、野沢慎司編・監訳、2006、『リーディングスネットワーク論――家族・コミュニティ・社会関係資本』勁草書房:123-158)を発表し、その後も第一線で活躍している。
田丁町舞網在住(危篤薬局勤務) 高梨佐緒里
(髙橋かおり/文化社会学/http://researchmap.jp/k.artkhs/)